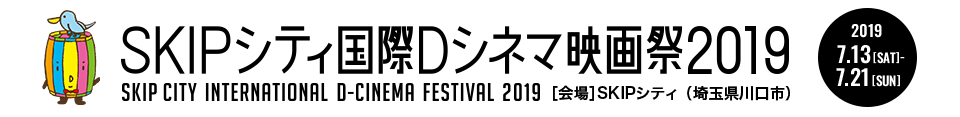ニュース
【インタビュー】国内コンペティション長編部門『サクリファイス』壷井濯監督

『サクリファイス』
壷井 濯 監督インタビュー
——こちらは第1回立教大学現代映像身体学科スカラシップ作品とのこと。これはどういった制度なのでしょう?
大学としては初の試みということでした。ただ、学科の教授である篠崎(誠)先生や万田(邦敏)先生は、ずっと学生たちが作品を作れるような支援制度ができなかと考えていたそうです。
——学科内の学生を対象にした企画コンペということで間違いない?
そうですね。審査には篠崎先生や万田先生ら4名の先生が当たってくださって、2つの企画が選ばれました。そのひとつが僕の『サクリファイス』になります。
——その講評ではどんなことを?
これがなかなか厳しくて(笑)。『サクリファイス』に関しては、賛否で意見が真っ二つに分かれていました。2名の先生には、酷評されて(苦笑)、その時点では「これは通らないな」と諦めたぐらいです。簡単に言うと、人間とその心情がきちんと描けていない、何を描きたいのかわからないと。
一方で、もう2名の先生はすごく支持してくれました。何を隠そう、ゼミの教授である篠崎先生と、演劇分野の専門家である相馬(千秋)先生だったんですけど、お二人は「内容うんぬんではなく、とにかくあなたがこれをやりたいんだ」という気持ちが伝わってきたと。相馬さんは、全部みた中では「これしか見たいと思う作品がなかった」とまでいってくださいました。その言葉にはすごく励まされました。
——そして無事に企画が通ったと。その脚本ですが、猫殺しや殺人事件など周辺で不穏な事件が相次いでいる大学が舞台。今は脱会しているがかつて新興宗教で東日本大震災を予知したことのある女子大生の翠、同級生で猫殺しの犯人と噂される沖田、沖田を執拗に敵視する塔子という3人の関係が複雑に絡み合ったドラマが展開していく。物語の背景にあるのは、カルト宗教、大災害、未来予知、戦争といったどこか世紀末を感じさせるもの。これはどういったところから生まれてきたのでしょう?
そもそもは授業の課題で震災をテーマにして書くことになったんです。それで震災について向き合うことになりました。その時、思い出したのが震災時、多くの映像作家およびクリエイターと呼ばれる人たちが現地に入って、震災関連の作品が生まれました。それについて特に意見はないのですが、僕はなにかそれまで人の心や内面といった個人の小さな世界の声を丹念に拾っていた作家たちまでが、なにか対外的にわかりやすい震災という大きな出来事の全体でしかとらえないようになっているように映って、そこにすごく違和感を覚えました。あくまで個人的な感触に過ぎないのですが…。
こういう時こそ、人間の内面を掘って掘って、その先にあるものを見せるべきではないか。それこそが寄り添うことであり、個人の心に届くのではないかと思ったんです。それで、絶望の先にある希望のようなものを描いた物語を作りたかったところがあります。
あと、先ごろおきた川崎の通り魔事件とか、かつてのオウムの事件や秋葉原の事件など、世間を震撼させるような事件が起きたとき、「信じられない」「人間じゃない」といった犯人を全否定することで収めてしまう。排除して終わってしまう。恐れずに言うと、それでいいのかなと。もちろん人を殺すことは許されない。ただ、彼らもこの世の中に確かに存在していた。その存在を全否定するだけで終わっていいのかなと。
誰しも心に闇を抱えている。もしかしたら、自分も一歩間違えば、彼らのようになってしまうのではないだろうか?と僕は感じるときがあるたびたびある。そういった危機感、たとえば心にぽっかりとあいた空洞に、何かすっと悪いことが入り込んでしまう。その前に、代わりに隙間を埋められる様な物語を描けないかと思いました。
——この物語の世界で、篠崎(誠)監督、黒沢(清)監督の現場も経験したことがある。そうなると、たとえば『大いなる幻影』などの黒沢清監督のディストピア作品の影響はあったのかなと?
そうですね。黒沢監督の作品は大好きなので影響を受けていないといったらウソになります。『サクリファイス』の脚本も黒沢作品に似すぎていると指摘される個所があって、そこは事前にカットしていきました。
もちろん、黒沢監督が2000年前後に発表したディストピア作品は通ってきているんですけど、自分はもうひとつ後の時代といいますか。いわゆるセカイ系と称されている、男女の個人的な小さな関係性が、世界の危機につながっていくような、どちらかというとそういうことをやりたいなと思いました。
——そういわれると、主人公の3人の配置はよく考えられている。沖田は何事があってもまったくぶれない。世間の目など気にしない。個人の人間として立っている。一方、翠は自責の念をもっていて、社会と自身の間で常に揺れ動く。そして塔子は一方的な見方しかできない人物で。悪とみなした沖田を徹底的に糾弾しようとする。なにか大きな事件が起きたときに見られる日本社会の反応の縮図になっているといっていいかもしれない。
そう言っていただけるとありがたいです。

『サクリファイス』場面写真 ©2018立教大学映像身体学科/Récolte&Co.
——ただ、そうした社会性を帯びながらも、ストーリーとしての面白さも追求していますよね?
社会に対して自身が感じていること、知りたいことを描いてはいるんですけど、物語としてはどこかエンターテインメントを追求したいなと。サスペンス・ストーリーの要素を入れたのはそこに理由があります。
——ただ、こうした漠然とした不安や失望といった感覚を映像で表現するのはなかなか難しいですよね。変な話、スタッフに説明するのも難しいのではないでしょうか?感覚的な部分が占めるところが大きいので。
それはけっこういろいろな方に言われました。篠崎監督の『SHARING』の脚本を手掛けておられる酒井善三さんにシナリオを見ていただいたんですけど、こういわれました。「脚本ではサラっと目を通せるけど、果たして映画として成立できるのかな」と。
僕は、以前から恥ずかしいんですけど、ヴィジョンが浮かばないというか。脚本を書いているとき、「このシーンはこうやって成立させる」とかまったく考えられない。まず、とにかく書きたいように書く。
おそらく多くの映画監督は、たとえばある一場面があったとしたら、それを絵で覚えると思うんですよ。僕はどちらかというと文字で記憶するタイプといいますか。すべてを文字でまず考えてから、次にようやく画を考えることができる。文字がまずありきなんです。だから、他人から「このシーンでこのセリフはちょっと臭すぎないか」と言われて、はじめてそのシーンのトーンとセリフがどうも食い違っていることに気づいたりするんです。
——文字化することで、はじめて画も頭に浮かんでくる?
そうなんです。立教大学はわりと、撮ってなんぼみたいな人が多くて。脚本とかなしでとりあえず映像を撮ってみるという人が少なくない。それで僕もちょっと「脚本なくてもできるよ」みたいにかっこつけてやったりもしたんですけど、やっぱりダメで(苦笑)。それからは恥ずかしがらずに書くことを重視するようになりました。
——キャストの方についても聞きたいのですが、まず、沖田役の青木袖さんはどういった経緯で?『コーヒーが冷めないうちに』や『累―かさね―』など、話題作への出演を果たしている若手です。
若いキャストは、翠役の五味(未知子)さんを除いては全員オーディションです。実は、沖田はほんとうになかなかみつかりませんでした。セリフを言ってもらったんですけど、こちらに響く形で言える人がほんとうにいない。どうしようかなと思っていたんですけど、最後に青木さんが来てくれて「これだ」と。初めてしっくりきたんです。それで、こういう気持ちわかりますかと尋ねたら、「わかります」と。じゃあお願いしますとなりました。
——五味さんはオファー?
そうですね。翠役は沖田以上に見つからなかったんですよ。それである日、動画を見ていたら五味さんが歌っている映像があって。それがちょっと緊張気味で、なにか怯えているようにも映る。でも、すごく一生懸命に歌っていて、ちょっとこの人に会ってみたいなとなあって、コンタクトしてみたんです。実際にお会いしたら、翠にぴったりで、お芝居の経験はゼロだったんですけど、お願いしました。
――若いキャストを支える脇役がひじょうに豪華ですね。
ええ。翠の母親役の三坂知絵子さんは、立教のほかの作品にもけっこう出ていらして、脚本を書いている段階から想定していました。
草野康太さんは、以前、僕がちょっと舞台に出演したことがあったんですけど、そのときご一緒して。『岬の兄妹』の和田(光沙)さんも一緒だったんですけど、僕は異分野からの出演だったので、けっこう周りから冷たくされたんですよ。でも、草野さんと和田さんだけはすごく優しくて、いろいろとアドバイスもしてくれた。その縁で、お願いできないかなと。
三浦貴大さんはほんとうにダメもとでお願いしたら、OKということでびっくりしました。
このお三方の役はいずれもほぼワンシーンのみの出演なんですけど、そこで強烈な印象と存在を放たないといけない重要な役で、実は生半可な役者では説得力を出せない。それを見事にやってのけてくださって、プロの役者のすごさを目の当たりにした気がします。
——初の長編作品を完成されていまどんなことを?
小学校の頃から劇や映画が好きで、中学生ぐらいから映画監督を意識するようになって、この道を進んだんですけど、まず入ったのが日本映画学校で。ここはわりと現場主義で、現場で映画のノウハウを学ぶ感じでした。そのあと、立教大学に進んで。こちらはわりとアカデミックで、映画理論からはじまって学んでいく。ある意味、両極を学べたことは自分にとってすごく大きな経験になっている。その間に、篠崎監督や黒沢監督の現場に参加させていただいて、いろいろと学ばせていただいた。
そういった経験を経て、大いに影響を受けながら、自分ならではの作品が今回できたかなと思っています。
上映当日、会場でどんな反応があるのか楽しみです。
(取材・文:水上賢治)