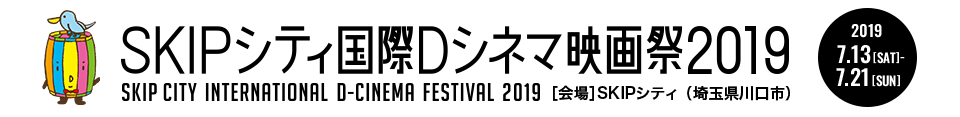ニュース
【インタビュー】国内コンペティション長編部門『おろかもの』芳賀俊監督
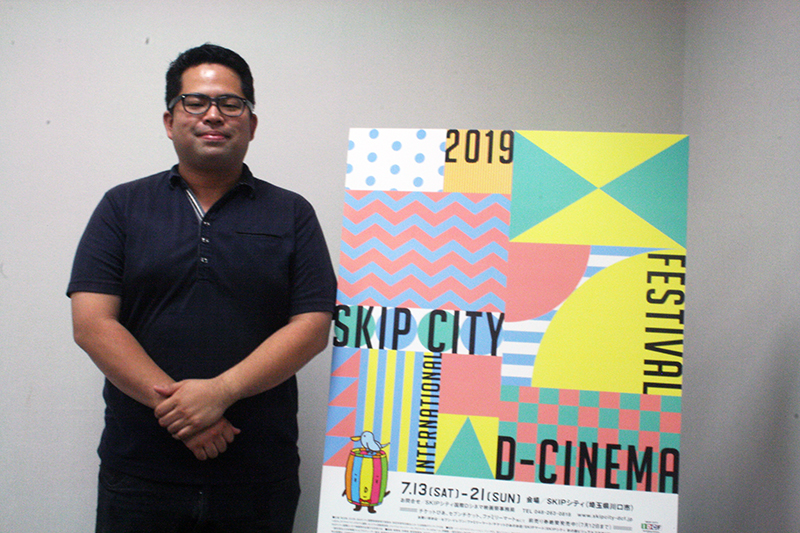
『おろかもの』
芳賀 俊 監督インタビュー
——今回の『おろかもの』は、鈴木祥監督との共同監督での作品。最初に鈴木監督との関係性についてお伺いしたいと思うですが?
日本大学芸術学部映画学科の同期です。彼は監督コースで、僕は撮影コースだったのですが、入学して1週間ぐらいで意気投合して、こいつと一緒にずっと映画を作れたらいいなと思ったぐらい。入学したのが2007年なので、もうかれこれ12年以上の付き合いです。
——なにがそれほど気が合ったんですか?
日芸って最初に研修でバスに乗って軽井沢に行くんですよ。そのとき、バスで隣り合わせになったのが実は今回の脚本を担当した沼田(真隆)で。ものすごく意気投合したんですね。それで現地について、最初の課題が研修所の敷地内で各々好きな写真を撮るというもので。このとき、偶然一緒になったのが監督コースの鈴木くんで、これまた話したらすごく気が合う。
具体的には、評判はあまりよくないけど、自分にとっては光っている映画みたいなのがあるじゃないですか。そういう映画がことごとく一緒で。「この映画、オレ好きなんだけど」というと、「俺も俺も」みたいな感じになって。なんか3人はDNAがどこか同じなんじゃないかなと思ったりします。それぞれ認め合え、切磋琢磨できる仲間ですね。
——大学時、沼田さんは脚本コースだった?
いや、それが違って、僕と同じ撮影コースだったんです。今回の作品でも脚本だけでなく特機や照明のスタッフとしても参加してくれたんですけど、沼田は大学の時から脚本に抜群の才能があって、ちょっとこちらも驚くようなスケールの脚本を書く人だったんですよ。たとえば、遊郭が燃え落ちるとか。そんなの「学生映画では撮れません」というものばかり。ただ、実際にできたら、すごい作品になるんじゃないかという脚本を書く人だったんです。撮影コースなのに(笑)。
——では、今回はどんな経緯で沼田さんにはお話しを?
僕がさまざまな撮影現場で出会ってきた女優さん、まさに今回の主演を務めてくれた(笠松)七海さんとかなんですけど、彼女たちでいい映画が撮れないか常々話していたんですね。それで、ある時、沼田に「なにかいい脚本を書いてくれないか」と。そうしたら、2カ月後ぐらいだったでしょうか、沼田から、あらすじができたので読んでくれないかとなって。こんな話なんだけど、どうだと。それを読んだ瞬間に、やろうと思いました。
——それほど、心惹かれるものだった。
普段、僕は撮影部として活動してますけど、これは監督もしたいなと。それぐらいストーリーを読んだだけで、このシーンはこんなロケ地で、こんな風にカット割りをしてとか、イメージが一気に広がってしまいました。これはすばらしい脚本だと思いました。
——もうひとりの鈴木監督の反応は?
ぜひやろうと。同意してくれましたね。
——具体的には、脚本のどこに引き込まれましたか?
冒頭のシーンから驚きましたね。この作品は高校生の洋子が結婚を間近に控えた兄の健治の浮気を知り、その現場を押さえるところから始まります。普通に起承転結を考えたら、まずスマホなりなにかしらで兄の不貞を洋子が知って、後をつけて、浮気現場を押さえるという流れで構成していくわけです。ところがこの作品は、いきなり洋子が浮気現場をカメラで抑えるところから始まる。通常は事件が起きるまでの過程を追っていくと思うのですが、そこが一切はぶかれて事件がすでに起きているところからスタートしている。「さすがだな」と思いました。
また、もうその冒頭を読んだ瞬間に、僕の頭の中でビジュアルも浮かんでしまったんです。何かを見つめている洋子の顔があって、彼女がカメラをこちらのほうにむけて撮る。これはハイスピードで72コマで撮ろうとか、レンズは50ミリがいいなとか、光の具合はこれぐらいがいいとか、場所はこんなところがいいなとか。ほんとうにいろいろとイメージがわいてきて興奮しました。

『おろかもの』場面写真 ©2019「おろかもの」制作チーム
——物語は、高校生の洋子が兄の健治の浮気相手、美沙に好奇心から近づいたところ、糾弾するつもりだったのがどこか共鳴してしまう。すでに義姉のようにかいがいしく面倒をみてくれる兄の婚約者、果歩に悪いと思いながらも、美沙と破談にむけて共犯関係を結んでしまう。複雑な女性心理を精緻に描いています。監督ふたり、脚本家、いずれも男性にも関わらず(笑)、すごいですね
常日頃から、鈴木や沼田とはフェミニズム的な話をしていたんです。日本は男女格差、とりわけ男尊女卑の価値観からいまだに抜け出せていないのではないかと。たとえば、芸能人の浮気が発覚したとき、ケースにもよりますけど女性側のほうに「ふしだら」といったレッテルが貼られるケースが多いのではないでしょうか。男性よりも女性がものすごく叩かれるケースが多い気がします。あと、映画やドラマを観ていて、男性に主体があって、女性の存在をすごく軽く扱ったものがいまだに多い気がしてならない。
僕や沼田や鈴木は、そういうのを観ていて、常日頃からちょっと憤りを感じていて、その思いを共有していたところがあったんですね。なので、女性をひとりの魂を持った人間として描こうとずっと考えてきました。
——もっと、女性をきちんと描くべきだと。
そうですね。きちんと女性を描くことで、日本の今ある女性に対する風潮にも一石投じたいなと。
いま映画やドラマで描かれる女性は、たとえば必要以上に神格化されたたとえば母性の塊みたいな感じや、あるいは単なる性の対象であったり、もしくはイノセントの象徴、穢れのない者と極端な描かれ方をしていることがすごく多い気がします。例えば女子高生だったら、「かわいい」「少女」にすべてを集約させたようなタイプに仕立ててしまう。
でも、僕の周りを見た感覚だと、高校生はすでに大人。映画やドラマに登場するような、女の子、女の子しているような子はほとんどいない。そんな子どもっぽくない。自我がきちんとあって、自意識もある。
だから、女子高生の洋子もすでに社会人の美沙も同等に、ひとりの女性として描きたかったんですよね。果歩も含めて、現代を生きている女性として。
——確かに、洋子、美沙、果歩、いずれの女性もきちんと女性として立っている人物です。思いを共有する同性は多いかもしれません。
たとえば『マッドマックス 怒りのデス・ロード』は、僕は明らかにフェミニズムについて語っている映画だと思います。ただ、それに対し、こういう映画にそういうメッセージを持ち込むな、そういったものはこの映画の力にならないという声を寄せる人が少なからずいた。このことが僕はすごく残念で。メッセージは映画に大きな力を与えると、僕は思っています。
今回の『おろかもの』の核にはフェミニズムが確実にあります。めんどくさいメッセージはいらないという人もいることでしょう。でも、僕はそのメッセージが映画の魅力や力にならないことはないと主張したい。
この映画が、たとえば同じような境遇を体験した女性に届いて、少しでも心が和らいでくれたらうれしいです。
——その女性人物像を作るのに大きく貢献してくれたのが女優陣だと思います。まず、洋子役の笠松七海さんはどういった経緯でお願いすることになったのでしょう?
先ほど少し触れたように、今回は、僕がすごい魅力をもっていると感じた俳優さんたちに出演してもらったんですね。七海もそのひとりで。ある作品で会ったとき、どこまででもアップで撮り続けることができる女優だと思ったんです。ほんとうに見ていて飽きない。
だから、今回の作品もほとんど引きの画はないんです。ミドルとアップばかりで、洋子が見ている世界の話であるので、それが画としてもベストで。
アップにすると映える女優なので、彼女の魅力を最大限に発揮できたかなと思っています。
あと、見た目の話だけではなく、七海がすごいのは役として生きてしまうところなんです。
こういう脚本があって、こういうセリフがある、こう動くじゃない。その脚本にいる人になってしまうというか。その役の人物そのものになってしまうタイプの女優なんです。
だから現場では笠松七海を撮っているというよりも、洋子を撮っている感じで。ドキュメンタリーを撮ってるような気分になるんですよ。
こちらとしては事前に細かいところまでカット割りをつけてといった作業をするんですけど、実際に生きているように見えるので、もう「ここはもう割らなくていいか」「ここはそのまま撮り続けよう」といったことがしょっちゅうでした。いい意味で、こちらの計算をぶちこわしてくれて、すごかったです。
——美沙役の村田唯さんは、監督としても活動されているそうですね。
ええ。村田さんも実は日芸の同期で。彼女は演技コースで1年のときからの知り合いです。彼女の監督作品の現場にも撮影助手として参加しています。すばらしい才能の持ち主であることは大学時代からわかっていて、在学時から「彼女で何か撮りたい」と言っていたんです。でも、叶わなくて。だから、今回は念願が叶いました。
彼女も七海と一緒で役を演じるというよりは、生きるタイプ。脚本にまったく書かれていないことを平気にやってくるんですよ。たぶん、読み込みが深いので彼女の中でアイデアがあふれ出てくるんだと思います。
たとえば、留守宅に上がり込んで、健治のベッドに座りこんで、健治の髪の毛をつまむシーンがありますけど、あれは完全にアドリブです。脚本上に髪の毛なんてことはひと言も書かれていない。実は、髪を置いてもいない。本人にも見えていないんですけど、あんな所作を始めたんですね。これには驚きました。
——果歩役の猫目はちさんもまた監督としても活躍されています。
猫目さんは村田さんと仲が良くて、村田さんの監督した『デゾレ』でお互いスタッフとしてご一緒したんですけど、目力がすごいなと。猫目さんは、ある意味、目線ひとつでいろいろなことを語ってくれる女優さん。だから、セリフを落としたり、つけようとしていたしぐさをなしにしたりと、ここは猫目さんの目だけきちんと撮れていれば成立するという場面がいくつもありました。ほんとうに表情だけでなにかを物語ってくれる女優さんだと思います。
——猫目さんだけではなく、ほかの二人も目力がすごいですよね。
そこに惚れたところはあります(笑)。
——その女優たちの演出を含め、鈴木監督とはどういった役割分担をしていったのでしょう?
すごく気が合う鈴木と僕なんですけど、タイプは全然違うんです。たとえば画面のピントをどこであわせるかで、僕はアバウトにだいたいこのあたりかな、みたいな感覚に頼るタイプなんですけど、鈴木は「このシーンはこうこうこうだから、ここに置くべきだ」と理詰めできちんとした理由をもって導きだす。そうした自分の持っていない面をお互いに補完しあいながらやっていった感じです。たとえばある場面は、僕の感覚的なところを生かし、ある場面では、鈴木の理論を当てはめる。そうしたコラボで進めましたね。
——ひとつ、プロフィール的なところで映画を目指すきっかけは?
映画は子どものころから好きで、将来の夢は映画監督とか卒業文集に書いたような記憶もあります。ただ、決定的だったのは高校生のとき。進路をどうしようと考えていたころ、新聞にある映画の劇中写真を見たんです。テオ・アンゲロプロス監督の『エレニの旅』のワンシーンの抜粋写真だったんですけど、最初に目に飛び込んできたときは一枚の絵画かと思いました。それで映画を観にいったんですけど、驚きましたね。「どうやったらこんな映像を撮ることができるんだ」と。それで決心して日芸の撮影コースに進みました。
——今回の入選はどう受け止めていますか?
歓喜の極みといいますか。作っているときは、いま編集しているこのパソコンの中だけで誰にも見られずこの映画が完結してしまったらどうしようという、途方もない不安がつきまといました。ですので、入選の報告をいただいたときは、もう涙が出るぐらいうれしかったです。ここまでやってきたことがすべて報われた気がします。
僕の中では、これまで出会ってきた最高の役者とこれまでいっしょにやってきた才能あふれるスタッフが大集合して、全力投球して完成させた映画で。これまでの集大成的なことを感じる映画なので、最高の上映環境で上映されることがうれしいです。
あと、個人的なことなのですが僕が撮影助手デビューした『舞妓はレディ』は、SKIPシティで撮影されたんです。なので、ちょっと「ここに帰ってこれた」という気持ちがあって、感慨深いものがあります。『舞妓はレディ』の経験があったから、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭には絶対に応募しようと思ってましたから。締め切り当日まで作業して、滑り込みで応募したぐらい、「これは外せない」と思っていた映画祭だったので、ほんとうにお披露目となる当日を楽しみにしています。
(取材・文:水上賢治)